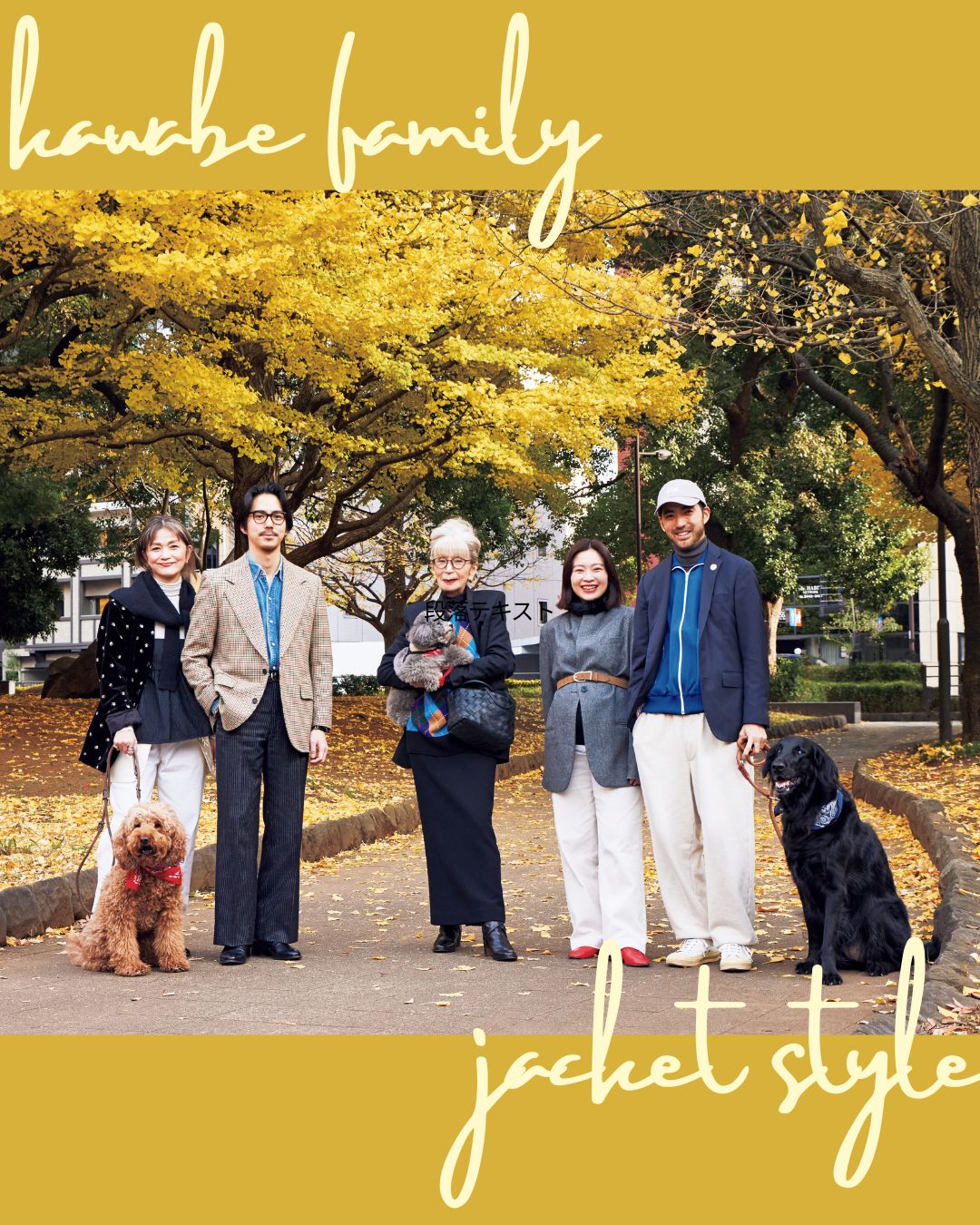PR
【対談】建築家・谷尻誠と〈LIXIL〉山崎弘之が語らう、未来を切り拓くテクノロジー

住まいや暮らしにまつわるさまざまな製品を手がける〈LIXIL〉。より豊かで快適な暮らしを実現するために、テクノロジーのさらなる更新を続けている。いま、そのテクノロジーはどこに向かっているのか。研究の最前線を牽引する、LIXIL Housing Technology 技術研究所所長でビジネスインキュベーションセンター センター長の山崎弘之さんが、建築家の谷尻誠さんとともに語ります。
山崎 私たちは製品性能やサステナビリティの向上を目指してイノベーションに取り組んでいるのですが、やはりエンドユーザーのみなさんに選んでいただくことが最も大切なこと。そのためにはどういう価値を加えていけばいいのかをお話ししたく、この機会をいただきました。
谷尻 よろしくお願いします。山崎さんたちはどのような製品を開発されているのでしょうか。

谷尻さんが手にするのは《revia(レビア)》。廃プラスチックと廃木材を原料に、押出成型した素材で幅広い活用が期待できる。

山崎さんから谷尻さんに素材を説明。さまざまな原材料から作られた再生素材で、その素地の色そのものに魅力がある。

LIXILの社内で作成した〈FORCE CARBON〉を用いた建築の提案。計量で強靭な素材は、さまざまな表現の可能性を秘める。

研ぎ出しの石材を思わせる《textone》。軽くて加工しやすいので、エクステリアだけではなくその他の製品への可能性も。
山崎 最初に意外なものを紹介させてください。既存事業の枠組みにとらわれず、〈LIXIL〉のハウジング事業の中で新しい価値を生み出す部門が、私が所属するビジネスインキュベーションセンターです。そこで開発した製品の一つがマグネット脱着式のキャットウォール《猫壁(にゃんぺき)》です。飽きっぽい猫は、既製品のキャットタワーだとすぐに飽きてしまうこともあり、自由度の高いプロダクトとして開発したものです。ただ、多くは環境性能を意識した建材の開発に力を入れています。サポーズデザインオフィスでは、そうした建材の利用をクライアントからリクエストされることもあるのでしょうか。
谷尻 クライアントから環境性能の高い商品をリクエストされることはまだ少ないですね。僕らが施主である〈猫屋町ビルヂング〉はリノベーションということもあり、なるべく既存の建材を残すことに注力しました。作らずに作ることが環境負荷の低減にも繋がります。そもそも化粧をするよりも素の美しさに魅力を感じるんです。それが個性になり、魅力になるのではないかと。

広島市中区にある歴史的な建物を沙ポーズデザインオフィスがリノベーション。歴史的建物の価値を尊重しつつ、空間を現代のニーズに合わせて再生。photo/Kenta Hasegawa
山崎 いま北海道で新たなプロジェクトを進められていますが、そこではどのように素材をお考えですか?
谷尻 自ら設計をしているにもかかわらず、建物はどこで作られているかも知らない建材でできてしまいます。食材はどの産地で、どの農家さんが作っているといった情報の透明性が求められます。けれど建築の世界はいまだにそう考えない。安全性や生産背景などに意識が及ぶことができていません。かつての住宅は、近くの森から切り出した木材で作られていました。なかなか力が及ばないこともあるけれど、北海道ではなるべく出所がわかるもので現代的な実践ができないかと考えています。まずは自分でやってみないと行動が伴わない(笑)。まずは小さな建物を作ることからはじめ、いまは土から畑を育てているところです。

谷尻さんは北海道美瑛町に計約6万平米の土地を複数人で共同所有。現在は小屋を建て、畑を造ったりしている。

大屋根が架かる住居は長野から古民家を移築する予定。

まずはサウナを建築。木を組んだプリミティブな建築で、原点に立ち返りながら計画を進めていく。
山崎 私たちが提案する循環型素材《revia(レビア)》は、再資源化が難しかった廃プラスチックと廃木材を融合させた新しい素材です。いまはそれぞれの地域で発生した廃プラスチックを活用できるような仕組みを考えているところで、これによってその場所に由来する建材となります。さらに、セメントとパルプをベースに、自然由来の素材感を無塗装で実現した窯業系の新素材《textone(テクストーン)》を開発しました。この素材には、廃屋の瓦なども混ぜることができ、これがまたいい意匠にもなります。
谷尻 建材のことを考える時、僕らはどうしても一点ものを作りたいという思いがあるんです。けれど現実にはカタログから汎用性のある建材を選ぶことも少なくありません。もし材料から開発できたらなによりもうれしいですね。また、一つの素材を一つの役割に限定してしまうことに疑問を抱えています。床にも壁にも使える素材は山のようにあるのではないかと思っています。これほど技術が進化しているので、もっと自由に素材を使うことができるといいなと思っているんです。
山崎 《textone》は椅子のような造作にも使っていただけます。見た目に反して非常に軽く、現場で木材のような感覚で加工することも可能です。タイルや石を現場で加工するのは大変なので、エクステリアの建材で加工しやすい素材は魅力だと思います。竹やもみがらなども混ぜ込んでいて、その表情を生かして使うことができます。構造用部材としての強度はまだ持ち合わせていませんが、視点をもっと広げていってもいいのかもしれません。アイデアを持つ建築家のみなさんの思いに応えられるかどうかが今後問われてくると思っています。
谷尻 建築家と建材メーカーがうまくタッグを組んで、より良い未来を作っていきたいですね。
山崎 ちなみに谷尻さんは釣りをされますよね? 釣り竿に使われるカーボンは軽くて強度があり、錆びません。けれど建築に使われることがほとんどないことはもったいないと思いませんか。いま私たちは炭素繊維強化プラスチック(CFRP)に注目しており、この素材を使った新しい住宅の表現を研究しています。まだ法整備が整っていないので提案段階なのですが。
谷尻 どうしても法律の速度はアイデアに比べて遅いですね。

《FORCE CARBON》は、CFRPを建材に適用・展開するため、これまで研究開発を進めるなかで蓄積されてきた〈LIXIL〉が持つ技術・ノウハウの総称。
山崎 ただ他の素材とCFRPを最適な構成で複合する《FORCE CARBON》はすでに住宅性能を向上させる技術として広がりつつあります。たとえばアルミとCFRPを組み合わせると、アルミ単体よりも強度を高めることができ、CFRP単体よりもコストを抑えることができます。コストと性能のバランスをとった最適な設計を行うことで、材料の使用総量も減らすことができるのです。パノラマウィンドウ《シームレス》はガラスエッジにCFRPを採用し、極細で凹凸のないフレームを実現しました。
谷尻 僕たちも例に漏れず、内外の連続性を実現するために繊細な窓を表現しようと努力しています。そのために細かなディテールを詰め、構造計算をしながらオリジナルサッシも作ります。けれど美しい既製品があるなら採用したい。やはり長い時間をかけて研究された製品には性能面の利点があります。若い頃は負けずにがんばってきたけれど、最近は僕らもクライアントも大人になってきたので「いいものはいい」と既製品を使うことも増えました(笑)。そして建材の多機能化にも期待したい。窓が光れば照明はいらなくなるし、窓が発熱してくれれば暖房はいらなくなる。発電する窓があれば太陽電池を屋根にのせる必要がなくなり、エネルギーも生みながら自然に溶け込む建築を考えることができるようになります。
山崎 実は、すでにそういう研究も始めています。
谷尻 どんどん統合することで住宅の情報量が減り、風景が美しくなるのは確かです。エネルギーも太陽光発電のほうがいいという意見もありますが、もしその土地に既存インフラが整っているならば活用するほうが理に適っている。新規で設置するエネルギーと比較するなど、何が正しい取捨選択かを考えなくてはいけません。
山崎 窓においても、適材適所でサッシを選ぶという提案に力を入れていきたいところです。たとえば樹脂製サッシのほうが断熱性能は高いとされていますが、樹脂製サッシの製造工程でどれほど二酸化炭素排出量があるかは理解されていません。温暖な地域ではアルミサッシやアルミ樹脂複合のハイブリッド窓が有効に働く面もあるのです。2025年内には天然木を用いたサッシを発売します。天然の無垢材を用いたサッシは技術的な難しさもありますが、いいものができたという自負があります。
谷尻 デザイン面からも木質化はどんどん進んでほしい。かつてはオーディオ機器も木製が多かったけれど、いまは家電然としてしまっている。そうするとインテリアの調和が難しいと感じることも。
山崎 建築の場合は肌触りも求めますよね。一方ですでに存在するプラスチックを再利用することにも力を入れたい。
谷尻 テクノロジーのその先にあるのは自然だという話を聞いたことがあります。たとえば照明器具そのものは見えないけれど明るいとか。僕らは外にいて明るさを感じるときに太陽を光源として意識することはありません。けれど室内では照明を光源として意識してしまう。理想を言えば照明がなくても明るいのであれば、それはとても自然な状態といえる。テクノロジーにはそのように物質自体をなくしていく力があると思うんです。
山崎 テクノロジーの先に自然があるという意味で、いまアルミニウムは都市鉱山と表現され、使用済みの家電などから回収し、再利用が進んでいます。都市に埋もれる既存のアルミニウム素材で十分にこれからの製品を製造することができ、それらの再活用こそが地球への負荷を低減することに繋がります。それを実現するのがテクノロジー。一方で私たちは、もっと住宅の情緒的価値を高めていきたい。どうしても利便性や機能性の高さを追求してしまうのですが、心に響く体験こそが人々に求められているように感じます。
谷尻 僕らはなるべく塗装を禁止しています。プラスターボードを張るならプラスターボードそのものの色で仕上げればいい。すべての材料には色と素材感があり、そこに余計なものを加えたくない。先ほどもお話ししましたが、それをそれらしく美しく使うこと。であれば、魅力ある素材が増えていくととてもうれしいですね。
山崎 豊かで快適な住まいの実現が〈LIXIL〉における命題。環境戦略と事業戦略の融合を中長期計画のビジョンに盛り込んでいます。そのためにもテクノロジーをますます磨いていかねばなりません。

対談はサポーズデザインオフィスで行われた。谷尻さんの既存の価値観にとらわれない視点に、山崎さんは大きな刺激を得た。

山崎弘之/やまざきひろゆき
1973年茨城県生まれ。〈LIXIL〉の前身である〈TOSTEM〉入社後、 建材研究所で主にアルミの研究に従事する。近年はほぼすべての廃プラスチックをリサイクル可能とした循環型素材《revia(レビア)》の開発などに携わる。

谷尻 誠/たにじりまこと
1974年広島県生まれ。2000年にサポーズデザインオフィスを設立。多数のプロジェクトを手がける傍ら、近年「絶景不動産」「tecture」「DAICHI」「yado」「Mietell」をはじめとする多分野で開業、事業と設計をブリッジさせて活動している。
photo/Masanori Kaneshita text/Yoshinao Yamada