秋の旅行シーズンにおすすめ仙台・民藝の旅!愛らしいこけしやだるまを見つけに

長かった夏もようやく終わりが見えてきた頃。「どこかに旅したい!」という欲がムクムクと起きていませんか?クウネルがおすすめする「大人のニッポン観光」。東北地方随一の都市、仙台はいかがでしょう?テーマは民芸。現代に適合しながらも素朴な形で残るこけしなどの郷土玩具を紹介します。
無垢で不思議なその子との一遇。
作並のえじここけし
約150年の歴史を持つとされる作並系こけしの継承者、平賀輝幸さんが即興で製作。えじこは昔、野良で幼い子を籠に入れ子守をした慣習に発し、今もポピュラーな形。作並系に特徴的な菊模様はその形から蟹菊の愛称が。

こけしばかりでなく宮城の伝統工芸品も充実。
こけしやだるま、張子など仙台で歴史ある民芸品と出会う旅は老舗民芸品店『こけしのしまぬき』から。「初めてこけしに興味を持った方が来られる場合が多いので、現役工人のスタンダードな作品中心に集めています」と社長の島貫昭彦さん。伝統こけしは全12系統をポップで解説しながら網羅、伝統こけし工人作の創作こけしも揃います。「仙台張子」の面や干支物、「松川だるま」、「堤人形」と仙台の民芸品も豊富。

『しまぬき』のビンテージ
このコーナーに並ぶのは昭和生まれのこけし。以前は物故工人の作品は値段の高騰を避けいったん店頭から外される習慣だったとのことだが、今は再び陳列され販売も。うちにもこんな子がいたような気が……。価格は様々。
「こけしは震災以降に再びメディアでも取り上げられ、新しいファンを獲得。現代のニーズに応え小サイズが主流です」と島貫さん。社長考案の明かりこけし、またこけし缶などのヒット商品も。

堤人形は藩政時代に仙台市堤町で生まれた土人形で、さまざま縁起物的な役割も担ったとか。猫と酉、巳。

雄勝(おがつ)硯、鳴子漆器、仙台箪笥、そして宮城伝統こけしという国指定の伝統的工芸品を核とし宮城、東北の手仕事のものを揃える。
こけしのしまぬき
住:仙台市青葉区一番町 3-1-17 しまぬきビル1F
電:022-223-2370
営:10:30〜19:00
休:第2水曜(8月を除く)、元旦
くりくり両眼のだるまさんは見守り元気づけるパワーが!
仙台藩士、松川豊之進が仙台張子を創始しだるまづくりを始めたのが起源と伝わる松川だるま。直伝を受けた本郷家10代目久孝さんと妻・尚子さんが「昔ながら」を守ります。
「『だるまさんをそばにおいて前に進みたい!』という人は多く、そんな思いに応え続けようと一部の成形だけ外にお願いしますが、2人の手作業で頑張っています。和紙や接着に使うツノマタなどの材料もできる限り変えず、伝統を守っていきたい」と尚子さん。豊之進から受け継ぐ型と製法による雀や俵牛等の張子は全部手作業。愛らしい顔ばかり!

『本郷だるま屋』の松川だるま
松川だるまは両眼入りで四方八方を見守るとされる。世の暮らしが変化し作り方や材料の一部は移り変わっても空と海を表す群青色やほっそりボディは不変。この「宝船」デザインは眉がふさふさの毛なのもユニークで可愛
昔は正月に3寸から始め1個ずつ大きいものを8個揃えたら1個ずつ買い替え、古いものをどんと祭でくべるのが習いだった。
本郷だるま屋
住:仙台市青葉区川平4-32-12
電:022-347-4837
営:10:00〜17:00
休:不定 来店は要予約。
伝統こけしと創作こけし両方の魅力を伝える。
鳴子や遠刈田など5系統の流れをもつ宮城県のこけし。そのひとつ作並へ。今は『平賀こけし店』の4代目、平賀輝幸さんが作並こけし唯一の工人です。「自由に好きなものをつくるのは楽しいですし、伝統も大切にしたい」と。えじここけしをろくろで削り出し、素早く描彩していく確信をもった作業に見とれます。可愛く穏やか、ベーシックな形のえじこが誕生。

左下は線段模様のこけし。他にもフルーツのせやモダンな花模様など、創作系もお得意。
作並こけしの特徴は蟹菊模様の他、細い胴、頭頂の一筋の髪等。仙台や東京等イベントや作品展に度々参加している平賀さん。

工房で祖父、父と3台ろくろを並べた時期もあった。製材、乾燥、木地作りから全部一人の手作業。ミズキやイタヤカエデの木地を削り滑らかにした後にろくろ模様を施している最中。そして筆描きで命が吹き込まれる。
平賀こけし店
営:仙台市青葉区作並元木13
電:022-395-2523
営:7:00〜19:00
休:不定 こけしの絵付け体験は3日前までの予約で可能。
写真/山﨑智世、取材・文/原 千香子
SHARE
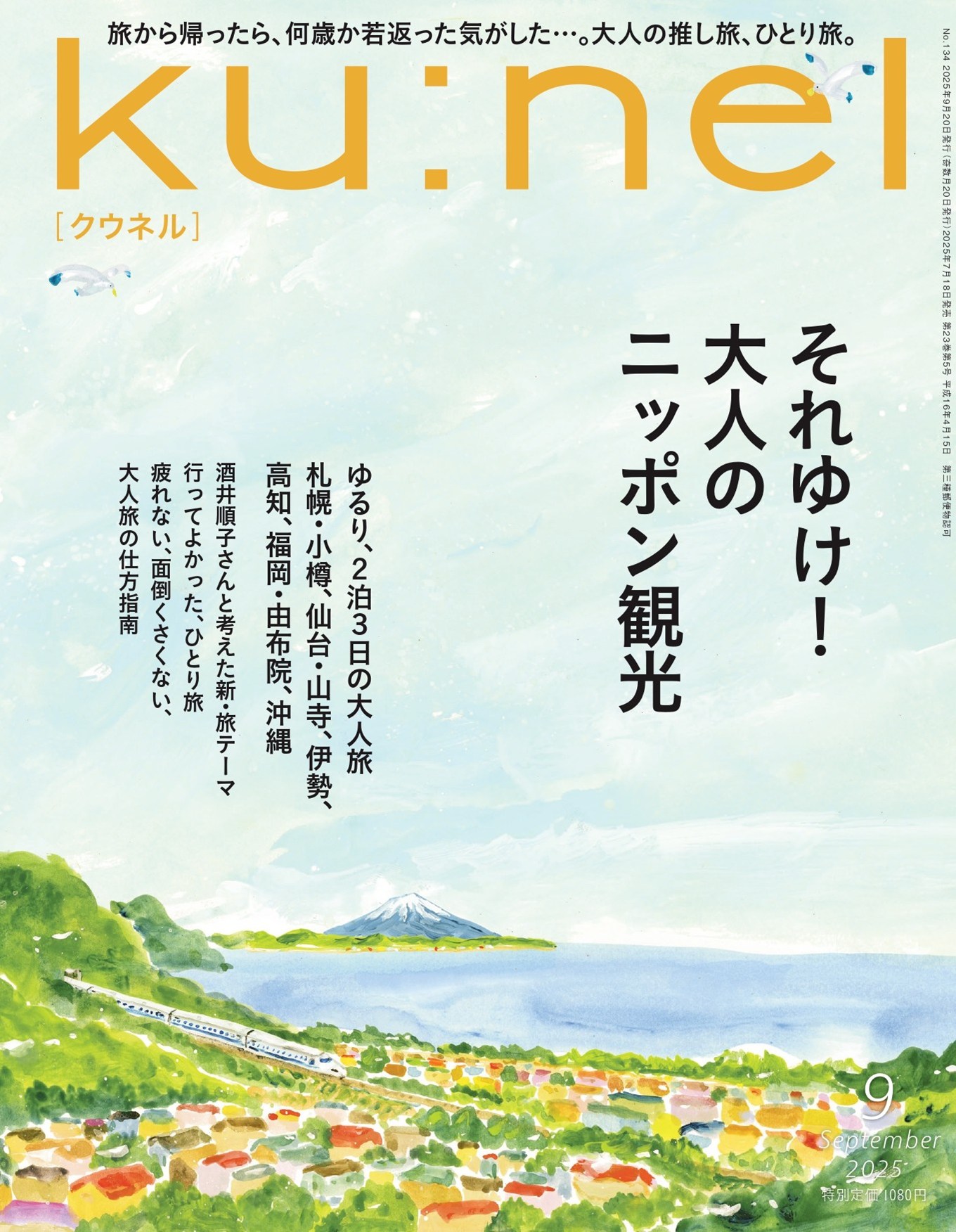
『クウネル』NO.134掲載
それゆけ!大人のニッポン観光
- 発売日 : 2025年7月18日
- 価格 : 1,080円 (税込)





















